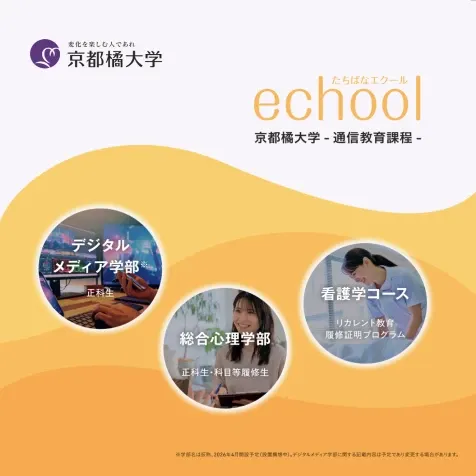心理学エッセンス
食と心理学
岸 太一
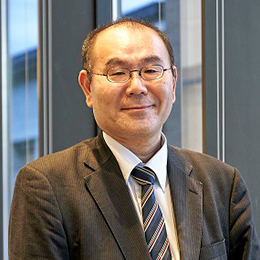
忙しい日ほど甘いものが欲しくなる,家族と食べるとつい食べ過ぎる,パートナーや子どもの好き嫌いに悩む——こういった経験をお持ちの方は多いのではないかと思います。これらのエピソードは,「食事・食べること」がいわゆる「身体の発達・維持」だけではなく,心理的・社会的側面を持つことを示す例であるかと思います。そこで今回は,「食の心理学」というテーマで,私たちの日常に重要な位置を占めている「食」を心理学の観点から見ていきたいと思います。
1. 食と感情
ストレスや不安は食行動に影響を与えます。「食べすぎる人」は気分を落ち着かせるために甘い・高脂肪の食べ物に手が伸びやすく、「食べなくなる人」は胃が収縮して食欲が落ちます。とくに“ストレス食い”の傾向が強い人は、ドカ食い→自己嫌悪→さらにストレス…という悪循環に陥りやすいことが知られています。
感情が食行動に及ぼす影響に関する研究によると,1)感情による食品選択の偏り,2)食品摂取の感情的抑制,3)認知的な摂食コントロールの障害,4)感情調節のための接触,5)感情に一致した摂食,の5つがあるとされています(Macht)。また,肥満に対する介入法に関する研究では,否定的な感情への反応として生じる摂食行動(いわゆるやけ食い)をとることが多い肥満者の場合はカロリー制限よりも感情制御能力に焦点を当てる方が良いことが指摘されています(van Strien, 2018)。
2.食と社会(孤食と共食)
家庭などで,誰かと一緒に食事をとらず,一人で食事をとることを孤食(個食)と呼びます。孤食は子どもでは肥満や偏食との関連が,高齢者では摂取する食品の多様性の乏しさやQOL(生活に質)の低さにつながることが指摘されています(Kimura et al., 2012)。
では,孤食と反対の「共食」ではどういった影響がみられるでしょうか。ある研究では,誰かと食べると食事時間が延び,食事量も増える「社会的促進」がみられることが指摘されています(de Castro, 1994)。また,同席者の食べ方に合わせる「摂食モデリング」や評価を気にして控える「自己呈示」も起こる事も知られています(Herman et al., 2003)。その他にも,一緒に食事をすることで,親密さや幸福感が高くなることも報告されています(Dunbar, 2017)。
3. 食と発達
食べ物の好き嫌いは親子で共通している場合があります。これは生物的な遺伝ではなく,「親が嫌いな食べ物を食卓に用意しない」ことで,子どもの食べ物の好みが親に似ていくのです。また,子どもが肥満の場合,親も肥満であることが多いのですが,これは親の食行動を含めた生活習慣を子どもが真似る(モデリング)ことで同様の体型になると考えられています。このように,幼い頃の食経験はその後の食行動につよい影響を与えます(Mahmood et al., 2021)。
ある研究では、家庭の食コミュニケーション不足、保護者の食への関心の低さや偏食、子どもの「こだわり」の強さが偏食を高めることが明らかにされています(當房他,2024)。また,家族での共食は子どもの自己肯定感や生活リズムの安定にもつながる。
4.まとめ
私たちは「お腹を満たす」ためだけに食事をとっているのではありません。自分の気持ちを落ち着ける,他者との良好な関係を築く,生活の質を高める-そういった目的のために食事をとることもあります。また,食事を誰かとともにとることでコミュニケーション能力を高めたり,問題解決のヒントを得たりすることもあります。
今回は「食」を心理学の観点から見ていきましたが,いかがでしょうか。今回の内容がちょっとでも「面白いな」とか「参考になるかも」と思っていただけたら幸いです。