心理学を学んだ後で見える世界は変わるでしょうか。
少なくとも毎日の身近な問題を考える上で、わたしたちにヒントを与えてくれるはずです。
例えば「今日はなぜ気分がすぐれないのかな」「なぜこの商品がよく売れるのだろうか」など、
自分やほかの人の心の動きについて客観的に理解することができるかもしれません。
「心理学エッセンス」では、日常生活のさまざまな場面を理解することに役立つ心理学の知見や基礎知識など
心理学をもっと身近に感じられる話を紹介していきます。
-
不都合を活かすという創造的問題解決
~日比野学長の退職記念講演「ネガティブ・ケイパビリティ」に寄せて~
#こころの健康
不都合を活かすという創造的問題解決
~日比野学長の退職記念講演「ネガティブ・ケイパビリティ」に寄せて~日比野先生が学長に就任された年に私もこの大学で勤務させていただくことになり、そして学長を退任される同じ年に、退職することとなりました。京都橘大学で過ごした日々を振り返ると、どこか不思議な気持ちになります。そ…
日比野先生が学長に就任された年に私もこの大学で勤務させていただくことになりそして学長を退任される同じ年に…
-
ボルダリングと心理療法

#趣味
ボルダリングと心理療法
皆さんはボルダリングをご存じですか?実は私、かれこれ5年以上ボルダリングを続けているクライマーなのです。ここでは、心理療法と私の趣味であるボルダリングを交えたお話をしようと思います。ボルダリングとは、ロープ…
皆さんはボルダリングをご存じですか?実は私、かれこれ5年以上ボルダリングを続けているクライマーなのです。こ…
-
レイルウェイ・カウンセラー始めました

#趣味
レイルウェイ・カウンセラー始めました
最近、レイルウェイ・カウンセラーを自称するようになりました。実は、前回の心理学エッセンスに「鉄道好きの妄想力」と題して書いたのですが、それを鉄道雑誌の編集者がご覧になったご縁で「旅と鉄道」2022年9月号(天夢…
最近、レイルウェイ・カウンセラーを自称するようになりました。実は、前回の心理学エッセンスに「鉄道好きの妄想…
-
ほどほどにのすゝめ
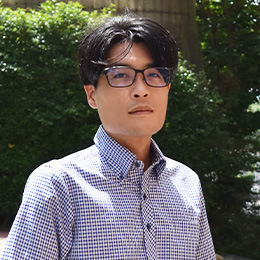
#子ども・教育
ほどほどにのすゝめ
みなさんは自分の子どものことをどれくらいわかっていると思いますか?通信生の方に質問すると,「90%はわかるよ」と自信をもって答えてくださる方もいれば,「全然わからない」と首をかしげている方もいらっしゃいます。…
みなさんは自分の子どものことをどれくらいわかっていると思いますか?通信生の方に質問すると,「90%はわかるよ…
-
I’ll be your hero ?

#趣味
I’ll be your hero ?
いつ頃からか、「異世界転生」というジャンルを見聞きするようになりました。本屋さんには専門のコーナーが設置され、異世界〇〇、転生したら〇〇、といった様々なタイトルが並んでいます。バナー広告で表示されるコミック…
いつ頃からか、「異世界転生」というジャンルを見聞きするようになりました。本屋さんには専門のコーナーが設置さ…
-
一人ひとりのこころと行動が社会を変える?「社会的ジレンマのしくみ」

#おすすめの心理学書籍
一人ひとりのこころと行動が社会を変える?「社会的ジレンマのしくみ」
皆さんにおすすめしたい心理学分野の書籍はたくさんありますが、私の専門とする社会心理学の領域で自分が読んで「これは面白かった!」と実感したものを紹介させてもらいます。もちろん、今回紹介する書籍以外にも面白いも…
皆さんにおすすめしたい心理学分野の書籍はたくさんありますが、私の専門とする社会心理学の領域で自分が読んで…
-
“丁寧”に過ごしたい!ーストレスマネジメントの視点からー
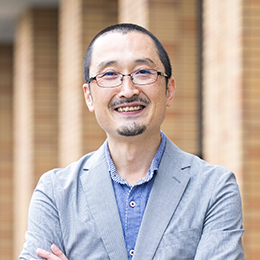
#こころの健康
“丁寧”に過ごしたい!ーストレスマネジメントの視点からー
何であんなこと言っちゃったんだろう?,そうだ,明後日の会議の準備をしなくちゃ,あっ,今日の夕飯は何にしよう?,そいえば草むしりもしないと...。この原稿を書こうとパソコンへ向かいながら,ついつい,あれこれ余計な…
何であんなこと言っちゃったんだろう?,そうだ,明後日の会議の準備をしなくちゃ,あっ,今日の夕飯は何にしよう…
-
子どもたちが教えてくれた「当たり前」を理論で説明することのおもしろさ-ストレスマネジメント教育の実践から-

#子ども・教育
子どもたちが教えてくれた「当たり前」を理論で説明することのおもしろさ-ストレスマネジメント教育の実践から-
日常生活と密接に関連する心理学という学問は、皆さまにとって、どのような魅力があるでしょうか?いろいろあると思いますが、私がおもしろさを感じるタイミングの1つに、「自分が何気なくやっていたことって、心理学では…
日常生活と密接に関連する心理学という学問は、皆さまにとって、どのような魅力があるでしょうか?いろいろあると…
-
ある父親の体験記

#子ども・教育
ある父親の体験記
いきなり私事で恐縮ですが,2024年現在の我が家には乳幼児が居ます。そうなると子育て関連のニュースが耳につきやすくなるのですが、その一つに妊娠や産後のうつがあります。このようなうつは、母親だけではなく父親もなり…
いきなり私事で恐縮ですが,2024年現在の我が家には乳幼児が居ます。そうなると子育て関連のニュースが耳につきや…
-
リーダーだって未完

#自分磨き
リーダーだって未完
四十不惑と言いますが、40歳を過ぎてもまだまだ迷うことばかりです。最近は「教育ってなんだろう」と考え、悩むことが増えました。まだまだ自分も未完であり、成長途中だなと感じます。しかし、これは私だけでなく、多くの…
四十不惑と言いますが、40歳を過ぎてもまだまだ迷うことばかりです。最近は「教育ってなんだろう」と考え、悩むこ…
-
人間関係はむずかしい?
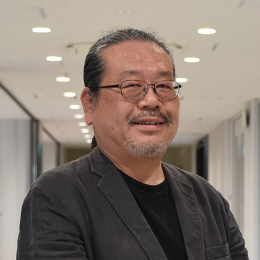
#コミュニケーション
人間関係はむずかしい?
カウンセリングとか心理療法ということを30年以上やっていますと、人間関係のもつれがきっかけでなんらかの精神科疾患にかかってしまったというクライエントさんがそのほとんどを占めていることがわかります。また、本学で…
カウンセリングとか心理療法ということを30年以上やっていますと、人間関係のもつれがきっかけでなんらかの精神…
-
失うからこそ得られる

#医療・福祉
失うからこそ得られる
「発達」を国語辞書で引いてみると、「成長して以前よりも大きくなること」とあります。実際、初期の発達心理学においても成人を完成体とみなし、そこにたどり着くまでの心身・社会的能力の獲得を中心としたメカニズムの解…
「発達」を国語辞書で引いてみると、「成長して以前よりも大きくなること」とあります。実際、初期の発達心理学に…
-
ベースの音に魅せられて出会った音楽の力

#趣味
ベースの音に魅せられて出会った音楽の力
ふと振り返ってみると、人生の半分以上の期間、ベース(呼び方は色々ありますが、弦楽器で一番低い音が出るやつです)に触れてきていることに気づきました。ベースとの出会いは、高校でオーケストラ部に入ることを決めた時…
ふと振り返ってみると、人生の半分以上の期間、ベース(呼び方は色々ありますが、弦楽器で一番低い音が出るや…
-
植物に「こころ」はあるのか?
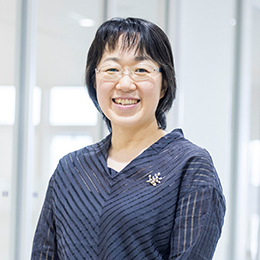
#趣味
植物に「こころ」はあるのか?
知人から月下美人を株分けしてもらって以来、植物に対する愛着が芽生えてきました。今では、リビングにポトスとオリヅルラン、ベランダに紫陽花と桔梗とシクラメン、そして月下美人の鉢を並べて、ささやかなガーデニングを…
知人から月下美人を株分けしてもらって以来、植物に対する愛着が芽生えてきました。今では、リビングにポトスとオ…
-
“逃げるが勝ち”って本当?

#こころの健康
“逃げるが勝ち”って本当?
「逃げるが勝ち」とは、一見逃げることは恥ずかしいことに思えるが、不利な戦いはせずに逃げたほうが結果的に勝利できる、という意味のことわざです。このことわざを、普段の生活のなかで実感することはありますでしょうか…
「逃げるが勝ち」とは、一見逃げることは恥ずかしいことに思えるが、不利な戦いはせずに逃げたほうが結果的に勝利…
-
かいじゅうたちのいるところ

#自分磨き
かいじゅうたちのいるところ
大学の私の研究室の入ってすぐのところに、「かいじゅうたちのいるところ Where the Wild Things are」(モーリス・センダック作、じんぐうてるお訳)という絵本を置いています。お好きな人も多い絵本ではないでしょうか。…
大学の私の研究室の入ってすぐのところに、「かいじゅうたちのいるところ Where the Wild Things are」(モーリス…
-
やっぱり、わかってもらいたい ―コミュニケーションのお話―

#コミュニケーション
やっぱり、わかってもらいたい ―コミュニケーションのお話―
ずいぶんと若い頃から、人とうまくつながるにはどうしたらいいのかと考えてきたような気がします。これは、家族で仲良く過ごしたいだとか、職場の人間関係を良くしたいとかいったことではなく(もちろん、それも含みますが…
ずいぶんと若い頃から、人とうまくつながるにはどうしたらいいのかと考えてきたような気がします。これは、家族で…
-
よい人生とは
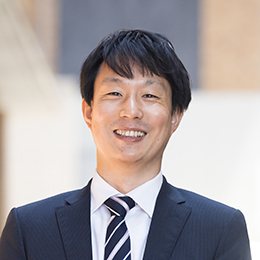
#お金・暮らし
よい人生とは
幸せとはなにか。よい人生とはなにか。中年期である私が、最近ふとしたときに考えることである。よい人生とは、偏差値の高い大学に進学することなのか、有名な企業で働くことなのか、あるいは、高い給料をもらうこと、タワ…
幸せとはなにか。よい人生とはなにか。中年期である私が、最近ふとしたときに考えることである。よい人生とは…
-
自分の行動は自分で決める……?

#こころと行動の関係
自分の行動は自分で決める……?
あなたは今日,目覚め,何か食べるなり飲むなりし,一歩は動き,この文章を読む,という状況に至っていると推察します。人間の生活は、いくつもの行動の積み重ねで成り立っています。では皆様は,なぜ,それらの行動をした…
あなたは今日,目覚め,何か食べるなり飲むなりし,一歩は動き,この文章を読む,という状況に至っていると推察…
-
人は思った通りに動いてくれない―過度な防犯対策による逆効果―

#こころと行動の関係
人は思った通りに動いてくれない―過度な防犯対策による逆効果―
次のことをイメージしてみてください。みなさんが住む地域の知事が「防犯対策を強化しよう!」と訴え,警察が町のあちこちでパトロールするようになりました。パトロールは昼夜問わずに行われ,警察を見かけない日がないく…
次のことをイメージしてみてください。みなさんが住む地域の知事が「防犯対策を強化しよう!」と訴え,警察が町の…
-
そのチケットの価値はいくら

#お金・暮らし
そのチケットの価値はいくら
2022年はサッカーW杯に日本中が熱狂しました。この記事を書いているのは3月上旬、まもなくWBC (Word Baseball Classic) が開催されます。2023年はバスケットボールやラグビーもW杯がありますので、スポーツ好きの…
2022年はサッカーW杯に日本中が熱狂しました。この記事を書いているのは3月上旬、まもなくWBC (Word Baseball…
-
理想的な休日の過ごし方? -記憶、海馬、運動の不思議な関係-

#こころと行動の関係
理想的な休日の過ごし方? -記憶、海馬、運動の不思議な関係-
日常の出来事を覚えておくことや心理学の用語を覚えておくことは、『記憶』と呼ばれ、心理学で盛んに行われてきた研究テーマのひとつです。期末テストや資格試験で必要な記憶は、集中学習よりも分散学習の方が、テキス…
日常の出来事を覚えておくことや心理学の用語を覚えておくことは、『記憶』と呼ばれ、心理学で盛んに行われてきた…
-
事実に基づき考えることの大切さ~高齢ドライバーによる交通事故から~

#医療・福祉
事実に基づき考えることの大切さ~高齢ドライバーによる交通事故から~
この原稿を書いているときに高齢ドライバーの交通事故のニュースが入ってきた。11月19日夜、97歳の高齢者が運転する自動車が数十メートルにわたり歩道を走行し,歩道にいた女性をはね死亡させたという。つい先日も高齢…
この原稿を書いているときに高齢ドライバーの交通事故のニュースが入ってきた。11月19日夜、97歳の高齢者が運転す…
-
小学校や中学校でみられる友人関係
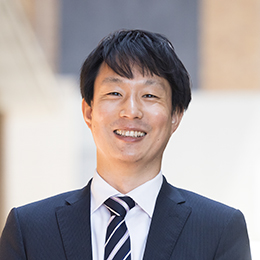
#子ども・教育
小学校や中学校でみられる友人関係
心理学を学んでいても、実際、心理学の知識ってどんなふうに役立てているんだろう?と思う方もおられるかもしれません。今回は、最新の研究論文を紹介するというよりも、私のスクールカウンセラー経験のなかで役に立…
心理学を学んでいても、実際、心理学の知識ってどんなふうに役立てているんだろう?と思う方もおられるかもしれま…
-
恋愛と免疫

#コミュニケーション
恋愛と免疫
数年前の出来事になりますが,ある結婚相談所が「DNAマッチング」というサービスを始めました。結婚を希望する人々のDNAを調べ,「相性が良いDNAを持つ人」を紹介してくれるそうです。正確にはDNAすべてではなく…
数年前の出来事になりますが,ある結婚相談所が「DNAマッチング」というサービスを始めました。結婚を希望する人…
-
他者とのつながりが人々を健康に保つ

#コミュニケーション
他者とのつながりが人々を健康に保つ
“Chronically lonely flies overeat and lose sleep.”これは2021年にNature誌に掲載された論文のタイトルです(Levine, 2021)。日本語に訳すと「慢性的に孤独なハエは過食と睡眠不足に陥る」となります。この論文では,キ…
“Chronically lonely flies overeat and lose sleep.”これは2021年にNature誌に掲載された論文のタイトルです(Levine, …
-
孤独だと寒いのは比喩じゃなかった

#こころの健康
孤独だと寒いのは比喩じゃなかった
暑い日々が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。京都は相変わらずthe盆地の気候で、湿度も気温も高いですから、蒸され続けている小籠包のような気持ちで日々を送っています。さて、真夏の、こんなにも暑い時期…
暑い日々が続いていますが、お元気でお過ごしでしょうか。京都は相変わらずthe盆地の気候で、湿度も気温も高いです…
-
机が汚いと仕事ができない?

#自分磨き
机が汚いと仕事ができない?
デスクが汚い人は仕事ができない,とよく言われます。この原稿を書いている机の上を見回すと,書きかけのノート,読みかけの本,読みかけの論文,水の入ったマグカップ,メモ帳,シャープペンシル,ハンドクリーム,ぬ…
デスクが汚い人は仕事ができない,とよく言われます。この原稿を書いている机の上を見回すと,書きかけのノート,…
-
子どもが笑う、大人が喜ぶ
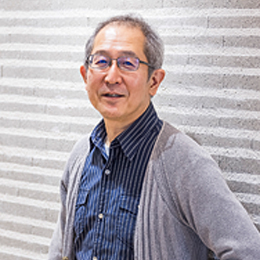
#子ども・教育
子どもが笑う、大人が喜ぶ
兄夫婦に初めての子どもが出来た時、私はまだ大学生でした。私の両親にとっては初孫で、生まれたばかりの赤ちゃんを全力であやし、笑ったと言っては大喜びでまたあやし、それはもう狂喜乱舞、見ていて大丈夫かなと心配…
兄夫婦に初めての子どもが出来た時、私はまだ大学生でした。私の両親にとっては初孫で、生まれたばかりの赤ち…
-
差別をなくすために大切なこと~善意の中に潜む差別~

#コミュニケーション
差別をなくすために大切なこと~善意の中に潜む差別~
先日、筆者が電車に乗っていると、ある駅で一人のお年寄りが乗り込んできた。すると一人の男性が何も言わずすっと席を立ち、そのお年寄りに席を譲った。何も言わなかったのは相手に気を使わせたくなかったからでもあっ…
先日、筆者が電車に乗っていると、ある駅で一人のお年寄りが乗り込んできた。すると一人の男性が何も言わず…
-
石の上にも三年-あきらめず成し遂げる力「グリット」-

#自分磨き
石の上にも三年-あきらめず成し遂げる力「グリット」-
MLBエンゼルスの大谷翔平選手は、「大リーグ初」という記録をいくつも打ち立て、日本のみならず、アメリカでも話題をさらっています。大谷選手に関するニュースや記事などを拝見すると、まさに自分とは別次元の「…
MLBエンゼルスの大谷翔平選手は、「大リーグ初」という記録をいくつも打ち立て、日本のみならず、アメリカ…
-
人に優しく、自分に優しく

#こころの健康
人に優しく、自分に優しく
先日、実習生を引率して、こども園にうかがってきました。実習の引率とはいうものの、子どもさんたちの屈託のない明るい笑顔に癒され、元気をいただきとても楽しい一日でした。その中で、とても素敵な光景にであいま…
先日、実習生を引率して、こども園にうかがってきました。実習の引率とはいうものの、子どもさんたちの屈託…
-
『ため息』の効能
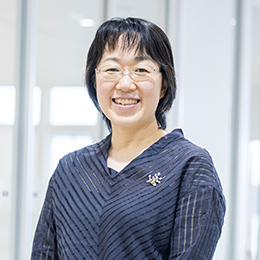
#こころと行動の関係
『ため息』の効能
忙しい朝の一仕事終えて「はぁ~」、大量のアイロンかけを済ませて「ふぅ~」、締め切りギリギリに課題を終えて「ふほぉぉぉ~」。今日もすでに、数えきれないくらいため息をついてしまいました。幸せが逃げてしまう…
忙しい朝の一仕事終えて「はぁ~」、大量のアイロンかけを済ませて「ふぅ~」、締め切りギリギリ…
-
喩えることのおもしろさ:自分を動物で喩えると…?
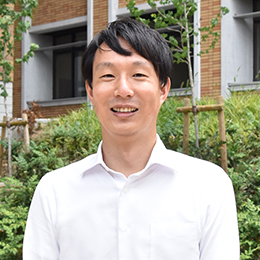
#こころの健康
喩えることのおもしろさ:自分を動物で喩えると…?
最近の自分自身を振り返ってみて、その状況を動物で喩えてみると、どのような様子の動物が浮かぶでしょうか? 働いているカバでしょうか?あぐらをかいているキリンでしょうか?あるいは、オスライオンのために働いてい…
最近の自分自身を振り返ってみて、その状況を動物で喩えてみると、どのような様子の動物が浮かぶでしょうか?…
-
「平穏な日々」を迎えるためにわれわれがすべきこと

#コミュニケーション
「平穏な日々」を迎えるためにわれわれがすべきこと
さて心理学はどのような学問だと思いますか?
これに対する答えは様々だと思います。一般的には「人間の心を読むこと=心理学」というイメージが強いです…さて心理学はどのような学問だと思いますか?
これに対する答えは様々だと思います。… -
鉄道好きの妄想力

#趣味
鉄道好きの妄想力
僕は「鉄」、鉄ちゃん、鉄道好きです。僕の「鉄」はわりと重度で、「鉄」によって自分の人生が決まってきたと言っても過言ではありません。たとえば、僕が中学受験を決意したのは、寝台特急(ブルートレイン)に乗りたかっ…
僕は「鉄」、鉄ちゃん、鉄道好きです。僕の「鉄」はわりと重度で、「鉄」によって自分の人生が決まって…
-
マインドセット -挑戦する過程を楽しめる心構え-

#自分磨き
マインドセット -挑戦する過程を楽しめる心構え-
勉強するのがつらい、スポーツで上手く結果がでない、そんな時、皆さんはどう考えるでしょうか?「この教科、理解するのが難しいけれど、一生懸命頑張れば自分の成長になる!」「今はつらいけど、努力すればきっともっと楽…
勉強するのがつらい、スポーツで上手く結果がでない、そんな時、皆さんはどう考えるでしょうか?…
-
嘘つきは知性の始まり
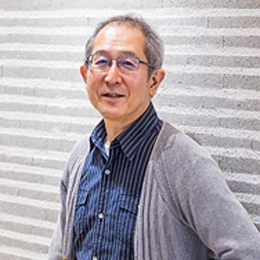
#子ども・教育
嘘つきは知性の始まり
嘘をついてはいけません。
これは当たり前のことですが、しかし全く嘘をつかない、生涯一度も嘘をついたことがない、そんな人がいるでし…嘘をついてはいけません。
これは当たり前のことですが、しかし全く嘘をつかない… -
コロナウィルスに対する免疫力~ポストコロナにおいて本当に大切なことは?~

#医療・福祉
コロナウィルスに対する免疫力~ポストコロナにおいて本当に大切なことは?~
5月末に緊急事態宣言が解除され,徐々にではあるが様々な活動が再開されつつある。ほっと安心するさなか,大正から続いてきた大阪の老舗フグ料理店の「つぼらや」が閉店した。さしものフグもウィルスには勝てなかったわけ…
5月末に緊急事態宣言が解除され,徐々にではあるが様々な活動が再開されつつある。ほっと安心するさ…
-
あと3日で地球が滅びるとしたら?

#こころの健康
あと3日で地球が滅びるとしたら?
あと3日で地球が滅びるとしたら、あなたは残された時間を誰と過ごすだろう?私たちが、3日後とは言わないまでも、5年後や10年後も生きている保証はどこにもない。しかし、普段そのことを意識して過ごすことは少ないだろ…
まあと3日で地球が滅びるとしたら、あなたは残された時間を誰と過ごすだろう?私たちが、3日後とは。…
-
笑う門には福来る

#こころの健康
笑う門には福来る
新年あけましておめでとうございます。「令和」という元号にもだいぶん慣れてきた感じのこのごろです。みなさまにおかれましては、令和2年・2020年の幕開けをお健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。…
新年あけましておめでとうございます。「令和」という元号にもだいぶん慣れてきた感じのこのごろで…
-
子どもは見ている、聞いている
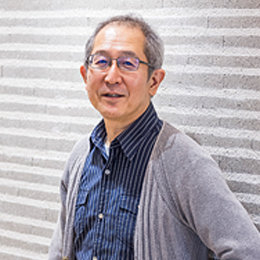
#子ども・教育
子どもは見ている、聞いている
ある程度言葉を話せるようになった子どもは、ことあるごとに「どうして?」「なんで?」と聞いてきます。何をどう答えても「どうして?」「なんで?」、そのうち面倒になって「どうしても!」「大人になればわかる!」…
ある程度言葉を話せるようになった子どもは、ことあるごとに「どうして?」「なんで?」と聞いてき…
-
やりたいことがうまくできない-自己制御の心理学から考える

#自分磨き
やりたいことがうまくできない-自己制御の心理学から考える
4月、キラキラと胸いっぱいに希望を抱いて新しい生活に踏み出した方、「今年度こそはこれをやるぞ!」と美しい桜の花に誓った方、多くいらっしゃるのではないでしょうか。かくいう私も今頃は英語がペラペラになっている…
4月、キラキラと胸いっぱいに希望を抱いて新しい生活に踏み出した方、「今年度こそはこれをやるぞ!…
-
心のなかにある財布(心理的財布理論)

#お金・暮らし
心のなかにある財布(心理的財布理論)
消費者が商品やサービスを購入した時に感じる「満足感」や,出費に対する「痛み」は、かならずしも支払った金額に比例するとは限らず、買ったものの種類や、それがどのような状況によって買われたかによって相対的に変化す…
消費者が商品やサービスを購入した時に感じる「満足感」や、出費に対する「痛み」はかならずしも支払った…
-
悪いストレスでも良いと思えば身体に良い?

#こころの健康
悪いストレスでも良いと思えば身体に良い?
突然ですが、皆様は今、どれ程ストレスを感じていらっしゃいますか?また、ストレスにどのようなイメージを持っていますか?ストレスというと「身体に悪い」「最悪なもの」というイメージを持つ方も多いと思います。しか…
突然ですが、皆様は今、どれ程ストレスを感じていらっしゃいますか?また、ストレスにどのような…
-
「人は人を支える」ということ

#コミュニケーション
「人は人を支える」ということ
人は人をなぜ支えようとするのでしょうか?
心理学においては,このテーマの源流は1960年代にアメリカの社会心理学者であるラタネらによって始められた…人は人をなぜ支えようとするのでしょうか?
心理学においては,このテーマの源流は1960年代… -
たちばな心理学の新著『心理学概論 -こころの理解を社会へつなげる』の紹介

#おすすめの心理学書籍
たちばな心理学の新著『心理学概論 -こころの理解を社会へつなげる』の紹介
本書ははじめて心理学を学ぶ人のために書かれた本です。京都橘大学健康科学部心理学科の教育課程「たちばな心理学」での出発点として、心理学の世界を紹介する世界地図としての機能を果たすように作られています。願わくは…
本書ははじめて心理学を学ぶ人のために書かれた本です。京都橘大学健康科学部心理学科の教育課程…
-
説得の方法

#コミュニケーション
説得の方法
「自分の考えを聞き入れてもらおう」として、ひとを説得しなければならないことは日常生活のなかでしばしばあります。このような場面では相手をどのように説得すればうまくいくのでしょうか?…
「自分の考えを聞き入れてもらおう」として、ひとを説得しなければならないことは日常生活のなかで…
-
商品の価値とは?

#お金・暮らし
商品の価値とは?
1日のうちに何度となく行われる商品の購買は、われわれ消費者が一定のコスト(支出)を支払って、商品に含まれる価値を手に入れるための行為ということになります。ではわれわれは商品に対してどのような価値を求めている…
1日のうちに何度となく行われる商品の購買は、われわれ消費者が一定のコスト(支出)を支払って…
-
社会心理学からみた「外見(身なり)」の大切さ(その2)

#お金・暮らし
社会心理学からみた「外見(身なり)」の大切さ(その2)
外見はまわりのひとびとの行動を変える
外見は「自己への効用」だけではなく「他者への効用」も有する。整った容姿は人々を惹きつけて他者との相互作…外見はまわりのひとびとの行動を変える
外見は「自己への効用」だけではなく「他者への効… -
社会心理学からみた「外見(身なり)」の大切さ(その1)

#お金・暮らし
社会心理学からみた「外見(身なり)」の大切さ(その1)
まずは自分の振り返りと反省から。
そもそも若い頃から身なりにはまったく無頓着であった。「大学のセンセーでベンキョー一筋だし、あんな格好を…まずは自分の振り返りと反省から。
そもそも若い頃から身なりにはまったく無頓着で… -
消費と広告の心理学

#お金・暮らし
消費と広告の心理学
私が専門としている消費者行動研究は「消費者の心や行動の仕組み」の客観的理解を目指す研究分野であるといえます。このような理解を行うための枠組みとしてK.レヴィンが提示した人間の行動に関するモデルが利用できます。…
私が専門としている消費者行動研究は「消費者の心や行動の仕組み」の客観的理解を目指す研究分野で…
-
やる気と報酬の関係について2-ほめるとやる気は高まるか-

#こころと行動の関係
やる気と報酬の関係について2-ほめるとやる気は高まるか-
一般的に人を『ほめる』ことは、望ましい行動の頻度や、やる気を高めるよいことだと考えられています。一方で、人をほめることはとても難しいということを、私達は経験的に知っています。誰の何を、どのように、どんなとき…
一般的に人を『ほめる』ことは、望ましい行動の頻度や、やる気を高めるよいことだと考えられてい…
-
やる気と報酬の関係について1-アンダーマイニング効果-

#こころと行動の関係
やる気と報酬の関係について1-アンダーマイニング効果-
スキナーが確立したオペラント条件づけの1つの型に報酬学習があります。お腹をすかせたネズミを箱の中にいれ、レバーを押せば餌がでるような環境に置くと、ネズミはレバーを押して餌を得ることを学習します。人の場合だと…
スキナーが確立したオペラント条件づけの1つの型に報酬学習があります。お腹をすかせたネズミを箱…
-
科学的であるということ

#こころと行動の関係
科学的であるということ
科学的に物事を考えるとはどういうことでしょうか?
科学的に考える時には自分の主観的な思い込みではなく、客観的な数値を示すことが重要です。…科学的に物事を考えるとはどういうことでしょうか?
科学的に考える時には自分の主観的な思い込みでは… -
ブランド志向の心理学

#お金・暮らし
ブランド志向の心理学
「日本人のブランド志向」はしばしば指摘されるところです。欧米人に比べて日本人のそれがより強く、また内容的にみた場合に「猫もしゃくしも」という感じの画一化の傾向が顕著であることは、アメリカの文化人類学者である…
「日本人のブランド志向」はしばしば指摘されるところです。欧米人に比べて日本人のそれがより強く…
